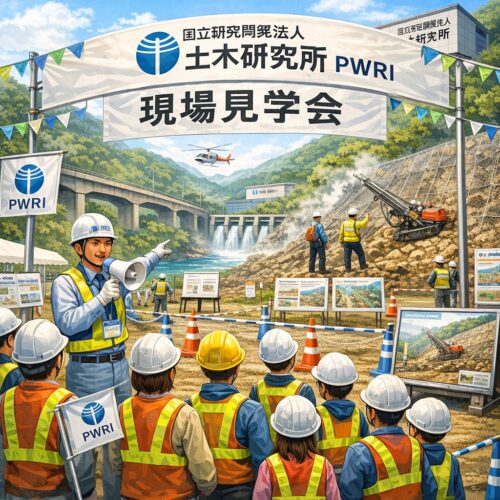皆さんこんにちは。
エンタです。
先日太田ジオの太田さんのブログで気になる記事がありました。
アンカー試験は定着部の性能を保証できない
記事の内容としては定着部+自由長部にグラウトが入るので
品質保証試験(多サイクル試験)はしっかりしたデータは取れない。
って事を仰ってます。

実際もそうですよね。
試験結果が下限値気味に出るのはその理由です。(摩擦部分が予定よりも多い)
定着部のグラウトと自由長部のグラウトは同じ物でつながっています。
アンカー自体は定着部のみがグラウトとつながっていますが、
周面摩擦の作用する部分は自由長部共に全てつながっています。
私は前々から言っていますが、品質保証試験で抜けなきゃOKって解釈です。
グラウンドアンカー工は抜けなければ施工は間違っていません。
試験データはぶっちゃけどーでも良いんですよね~(コレって言っちゃいけない?)
先生たちの論文で出ている以上は公に言っても良いようなw
コレも何回も言っていますが、そもそも1/100の試験を外でするなんてナンセンスだし、
不動点なんてまず取れないwww
データーに信憑性なんて微妙なわけですよ。
定着長部と自由長部にグラウトさえ入っていれば抜けないんです。
基本的には。
たまに抜けるアンカーもありますが、
それは定着部の考え方に問題があるという事になります。

グラウンドアンカー工は施工していてもまだまだ分からない事も多い工種で謎も多いですw
予定よりも自由長部が硬ければ抜けにくい。
自由長部が柔らかければ抜けやすいって言う考えも出てきます。
見えないところ(穴掘り)で仕事するって面白いですね。
また1つ考えさせられる事になりました。
それではまた。