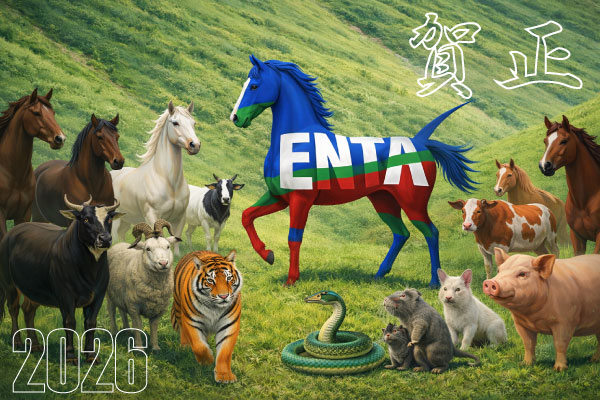皆さんこんにちは。
エンタです。

最近民間の工事で、大谷石の対策を言われてます。
土圧の対策や大雨対策は得意分野ではあるのですが、表面ですか!?
法面の対策はそんなに大した事ないんですが、石の風化対策となると我々法面屋はどうするか!?
そもそも大谷石とは!?
って思われる法面屋多いと思うので、AIの見解をコピペ
大谷石の歴史
● 栃木県宇都宮市大谷町で産出する凝灰岩。
約1,500万年前の火山噴出物が堆積し固まったもの。
● 古くは平安時代から使用。
寺院・石塔・石垣などに使われ、加工しやすさから日本各地に普及。
● 明治〜昭和初期に最盛期。
・蔵
・塀
・住宅の外壁
・学校・公共建築
などで大量に使用され、**「大谷町=石のまち」**として全国的に知られた。
● 戦後はコスト面と耐久面の理由から減少。
ただし近年は、独特の風合い・温かい質感が評価され
店舗デザイン・住宅・ガーデニングなどで再び注目されている。
大谷石のメリット(長所)
① 加工が容易(柔らかい石)
・ノミやカッターで切り出しやすい
・曲面加工・デザイン性の高い仕上げも可能
→ 施工自由度が高い、工期短縮にも向く
② 吸湿性・断熱性が高い
・無数の気泡(軽石状構造)があり
→ 夏涼しく・冬暖かい
→ 「蔵」に使われた理由のひとつ
③ 防火性が高い
・火山由来の石なので燃えない
→ 建築材料として安全性が高い
④ 独特の風合い(見た目が良い)
・淡い緑色~鼠色
・柔らかい質感
・経年変化が味になる
→ 店舗や高級住宅で人気
⑤ 比較的軽量な石材
・同じ石材(花崗岩など)に比べて軽い
→ 運搬しやすく、構造負担も少ない
大谷石のデメリット(短所)
① 吸水しやすく、劣化しやすい
気泡が多く柔らかいので
・水を吸う
・凍害を受ける
・風化しやすい
→ 屋外使用では防水処理・定期メンテが必須
② 強度が低い
・花崗岩や安山岩などに比べると圧縮強度が低い
・構造材には不向き
→ 主に **化粧材(仕上げ材)**として使われる
③ 施工時に欠けやすい
柔らかい石のため
・角が欠ける
・割れやすい
→ 慎重な施工が必要

大谷石とはこんな感じです。
法面屋であれば、モルタル吹いとけばイイじゃん!?
って思いますよね。
しかし、実際に民地で住宅用となるとなかなか養生や機械の場所など大変ですよね。
最低限の対策で最低限の施工を考えた場合、モルタルではないと思うんです。
となると樹脂系などのケミカル商品ですよね。
塗布して劣化防止的な。
それをイロイロ探しつつ、公共で実績のある製品をさがしてw
って思うと、公共で実績のある製品の強さってこう言う時に先に選ばれますね!
世の中の大谷石の対策工としては嘘ばかりが目立ちます。
と言うのも、地山崩壊を目的としているにも関わらず表面の石を風化しないようにする!って事だけを考えている。
これが間違いの根源。
根本は土圧や大雨対策のはずなのに・・・
石積の表面だけ綺麗にすれば良い的な。
コレは土木技術者として許せない案件なので、この辺をしっかり確立して行きたいと。
最近法面屋の仕事も有りますが、建築系の仕事もやらせて頂いているので、非常に面白い!
そして完全に他業種なので再勉強が必要ですが、刺激があります。
たまに他工種やると面白いのと似てます。(人によっては変化を嫌いますけど)
そして脳みそをフル回転させないと行けないので疲れますが、楽しさの方が勝っている今日この頃ですw
新しい事を少しずつリスクない形でやっていきましょう!
それではまた。