皆さんこんにちは。
エンタです。
先月私が削孔し、管理した水抜きボーリング工が完了したそうですw

最終の仕上がりが非常に良い感じで、綺麗ですよね!
1本30m弱の削孔で、削孔角度が7度なんです。
私はいつも思うんですが、角度付ける必要ないと思うんですよ。
最大でも3度程度でいいのでは?
確かにイロイロな文献に5度~10度と記載されているので設計者もそうせざるを得ないとは思うんです。
しかし逆に、じゃぁなぜ7度にした??
ってなった場合に明確な理由って無いと思うんですよ。
打設角度を水平(ゼロ)とし、30m削孔した時に
7度上方向に削孔した場合の30m先端部の高さは≒+3.7mになります。
(30m×tan7°)=3.68m
3.7mも上げる必要有る??
だったら、3度程度にしてもっと下から水を抜いた方が良くない?
って思うんです。
3度だと≒1.6m

地山が飽和状態になる時は下から徐々に水が溜まって行きます。
角度を付ける考えは雨が上から地山に入って行き上からパイプに入ると思っている方が非常に多いです。
水は水抜きパイプの下から入って行くので、
経験的に水抜きボーリング工は出来れば多段の方が効果的では?と思っています。
集水井の様な多段の形が一番理想ですね。
水は角度なくても流れていきます。
角度もゼロ~3度以内であれば問題無いと思っていますし、物理的に下方向の水抜きもあり?ではないかと思っています。
下方向の場合、地山の飽和度が観測出来る目安になる?(口元から水が出たらその位置が今ある水の位置)
まぁ今の常識を壊しながら新な施工を考えて施工していきたいです。
あとは過去に書かれた文献が邪魔をするだけですねwww
それではまた。





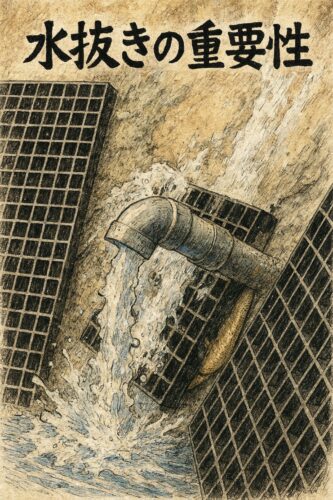


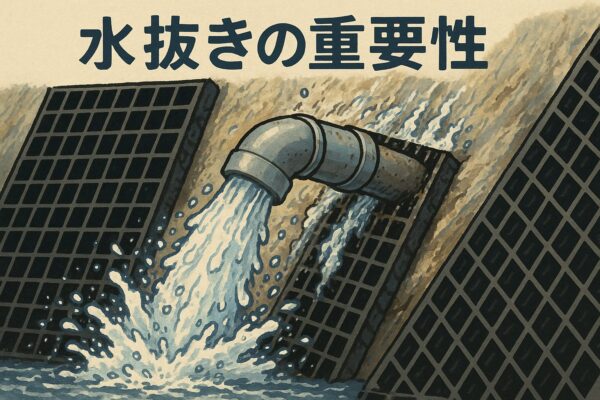
整然として綺麗ですねw
横管で連結する構造は初めて見ました!
毎回楽しく?はいけんしております。水抜きボーリング工の削孔角度についての今回も興味深く読ませていただきました。確かに色々な文献等をみると5~10度とありますね。「チコチャンニ叱られる」ではないですけど何故なんでしょうね?昔、と言っても40年位前ですが、新潟長岡の地滑り対策工事の時に一本が平均80m位の水抜きボーリング工を扇状に配置する仕様で施工した時に某コンサルの技術者が仰角を5~10度と設定するのはボーリング工の先端孔下がりを考慮しているからだと言っていたのを思い出しました。当時に比べれば使用機械の能力も数段向上しているでしょうし、あまり考えなくてもいいのかもしれませんが、長尺ボーリングの場合そのあたりはどう考えたらよいかまた教えて下さい。
お疲れ様です
たしかに先端が孔下がりします
なので上げておくっていうのは一つの手としてありかもしれません
下がる理由はケーシングの重さですね。
なので左下がりに行くようです
しかし、実際はどのくらい下がるのか?
っていうと、たしか資料有ったので次回のブログで書いてみます。
機械性能は今も昔もほぼ変わらないですねw