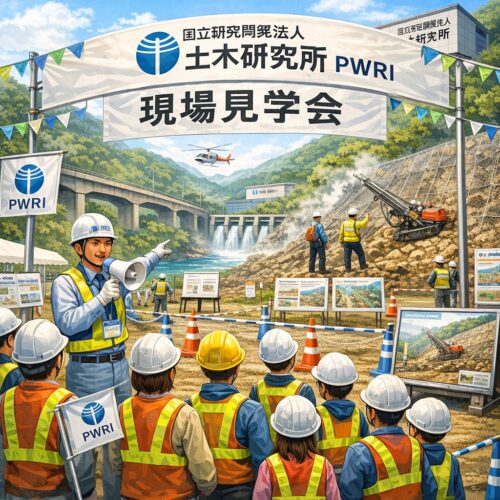皆さんこんにちは。
エンタです。
先日から小田原です!
小田原で石積崩壊対策補強工事をやっているんですが、一部コンクリート補修も入っています。
その為、千葉から左官仕事で応援をもらいました!
吉田官業のよっちゃんです!
真っ黒の特殊プレミックスモルタルを塗りつけて、我々土木では考えられない10㎜の仕上げをやってもらっています。
やはりプロってすごいなーって思いつつ眺めてましたw

閑話休題
パッカーの作り方講座(その5)
前回は先端でした。
今回は定着長部と自由長部の境目です。
この境目って実は結構難しいんです。
だいたい漏れるのはここからです。
実際は先端がしっかり締まっていれば、上部が多少漏れてても定着体としては大丈夫ですが、
加圧時に圧力ゲージが上がりきらないです。(上げすぎもダメですけど)
加圧時は出来るだけ0.2Mpaは超えない方が良いです。
0.5Mpaで注入ホースが爆ぜます!(実験済み)
そしてそれ以上で緊結部分が壊れる可能性かなり高くなります。
加圧しても削孔径以上は大きくなりませんし、
0.2Mpa以上はパッカー自体の網目が広がって逸脱するだけです。
上部が漏れていても大丈夫と言う理由は、
下部緊結部分壊れてなければセメントミルクの重量でパッカーは確実に膨らみます。
ただ上が開いているという状態なだけです。
見たことありませんが、全体のセメントミルク重量だけでかなり加圧されている
と言う事は物理的に分かりますよね?
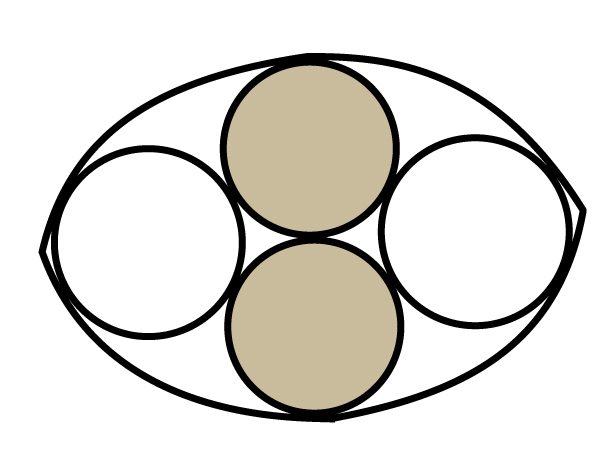
パッカー作成時の断面です。
例えば色つきの断面がPC鋼より線で、その横が注入ホースだとします。
注入用のホースと確認用のホースが2本あります。
パッカーをかぶせたらこんな感じで隙間ダラケになります。
それをスパンシールで埋めて漏れないようにするんです。
※スパンシール=ブチルゴム
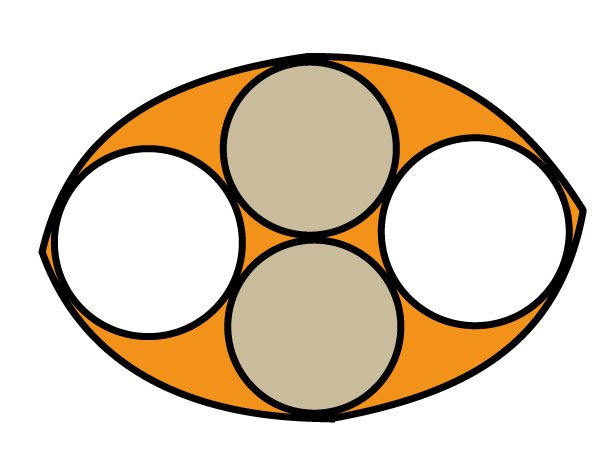
オレンジの部分がスパンシールになります。
意外にコレが難しいんですよ。

若い子に教えながらの作業ですw
この作業は地味で面倒ですが、大事な部分なので。

必ず1本の外周をスパンシールが回るように取り付けます。
スパンシール同士がくっつけば隙間が無くなります。

最終的にこんな感じの団子状になります。
スパンシールがしっかり付くようにして下さい。
この後はついにパッカーをかぶせていきます。
それではまた。