皆さんこんにちは。
エンタです。
今、秋田に来ています。
やっぱりサブイですw
しかし、緑化の時期ですね。
なぜこの時期に緑化をするのか?
まぁ普通に考えれば簡単な事なんですけど、
逆になぜ緑化が失敗するのか?
緑化が失敗した場合に考えられる事
- 霜で種が死んだ
- 1m2辺りの植生本数が多すぎて肥料切れで枯れる。
- 水分の保水性が悪い
- 肥料が多すぎて肥料枯れした。
- 獣害に食べられた。荒らされた。
- そもそも選出した種子がその地域に合わない。
- 暑さで熱枯れした。
- 土壌が汚染されている。
- ph値が極端に左右に高い。(酸性・アルカリ性)
- 水分が多すぎる土壌。(根腐れ)
- 土壌硬度が高すぎる。
と、考えられます。実際、種を入れてなかった、とかもあるんですがwww
いろいろな特殊条件などで生えない理由がある場合も、
春、秋と季節が安定している時期に施工すると案外上手く行くんです。
やはり生き物なので人間と同じく条件が良ければスクスクと育ってくれますw
緑化って簡単に言いますが、ホント難しいですよね。
しかも、瑕疵担保責任が2年もありますから。
それではまた。





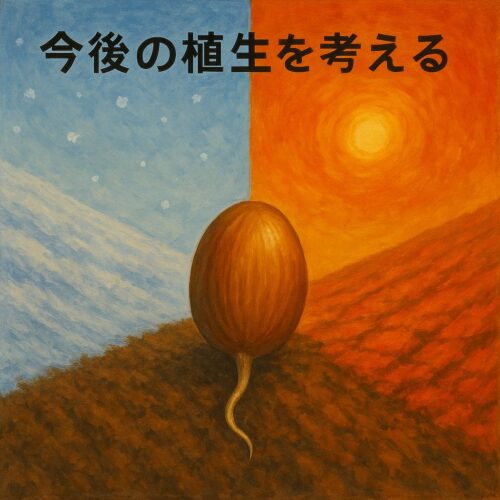

こんばんは^ ^
お伺いしたいことがありコメントさせていただきます。
枠内の設計が種子散布工になっており初めてこの工種の施工を行うのですが、植生基材吹付工の場合はいつものり面保護工選定フローや土壌硬度および酸度、降水量、法面勾配等を用いて吹付厚の選定を行い、種子の配合計画を作成し提出するのですが種子散布工も同じく調査検討書等提出の必要はありますか?
また、吹付に必要な種子の計算方法等ご存知でしたら教えていただきたいです。
いつもありがとうございます。
種子吹きでも調査は必要です。
役所の指示が妥当かどうかは施工業者がやるべき事です。
もしも、コレはおかしいと言う判断で有れば協議書で発現するべき事で、どちらに責任があるかを判断する材料です。
こう言う調査結果が出ました、役所から指示書を下さい。って言う方がスマートです。
それを調査無しで判断したとなると責任は誰になりますか?って事を考えた方が会社的にはいいですよね。
種子吹きの配合はネクスコのA吹、B吹を参考にするか、農林の仕様書を参考にすると良いですよ。
逆に言うと、役所に出させた方が無難です。攻めるのであれば、○○農林事務所のココに載ってる仕様を参照しました。
コレでよろしいですか?って言う協議書を上げた方がイイですね。
今後ともよろしくお願い申し上げます。