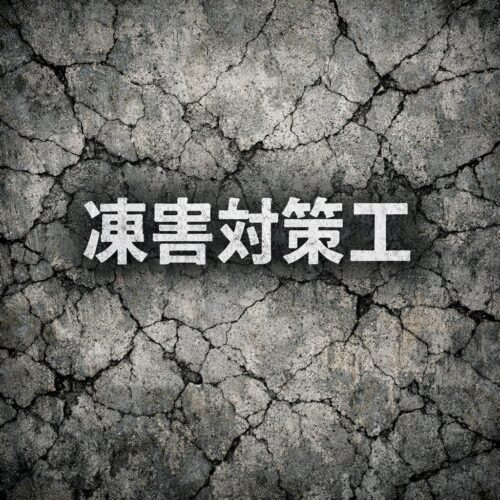皆さんこんにちは。
エンタです。
モルタル吹付はなぜクラック入るのか?
そしてそれの対策はどうするのか?
って事を書いてみようと思います。

クラックの原因を箇条書きで書いてみようと思います。
材料要因
- 水セメント比が大きすぎる(過剰な水分による収縮)
- セメント量が多すぎる(硬化収縮の増大)
- 骨材の粒度が不適切(細骨材が多すぎる、骨材の比重が低すぎる)
- 混和材やファイバーの撹拌不足や不適切使用
- 不純物を含む水や水がモルタルに適さない
施工要因
- 練混ぜ時間が不十分または過剰(分離)
- 練り置き時間が長く、硬化初期に施工してしまう(ボソボソ)
- 打設地盤が濡れていたり乾燥しすぎ
- 打ち継ぎ部での不適切な処理(打ち継ぎクラック)
- プラスチック製スペーサーの使用
- 吹付厚の不均等性
環境要因
-
高温時施工(蒸発が早く収縮ひび割れ)
-
低温時施工(凍害による微細クラック)
-
乾燥風・直射日光下と影の混在
-
周囲の湿度差による不均一乾燥
-
外部からの振動や荷重による硬化不良
設計・構造要因
-
打設厚さが不均一で応力集中(地盤の不陸が大きすぎる)
-
異なる部材の熱膨張差による応力(プラスチック製スペーサーとラス金網)

材料要因と対策
-
水セメント比が大きすぎる(過剰な水分による収縮)
→ 適正な水セメント比を守る(40〜55%程度が一般的)。必要に応じて減水剤を使用し、余分な水で調整しない。(暑い時はFT700Nで硬化を遅く) -
セメント量が多すぎる(硬化収縮の増大)
→ 強度に見合ったセメント量を使用し、過剰な配合を避ける。設計基準強度を満たす最低限の配合に抑える。(吹付機が小さい時代で37.5kgの時はバラツキ有った) -
骨材の粒度が不適切(細骨材が多すぎる、比重が低すぎる)
→ 骨材の粒度分布を確認し、適切な混合比で使用する。比重が低い骨材(軽量骨材)は用途を限定する。(地域によって差が出る為難しい部分もある 比重が低すぎると強度不足の原因にも) -
混和材やファイバーの撹拌不足や不適切使用
→ 配合規格に基づき混和材を適正に使用。施工条件(高温・低温・長期強度)に合わせた混和材を選択する。
ファイバーはしっかり撹拌しファイバーボールを避ける(夏場はFT700Nを1%未満で入れると良いがコスト↑↑) -
不純物を含む水や水がモルタルに適さない
→ 出来るだけ上水準の水を使用する。地下水や井戸水・河川を使用する場合はpHや塩分・有機物の有無を確認する。(練り混ぜ水試験)

施工要因と対策
-
練混ぜ時間が不十分または過剰(分離)
→ 規定の練混ぜ時間を守る(砂によって微妙に変わる為、各現場ごとに測って材料を確認)。オーバーミキシングを避ける。 -
練り置き時間が長く、硬化初期に施工してしまう
→ 練ったモルタルは出来るだけ早く使用。再練り(リテンディング)はダメ。 -
打設地盤が濡れていたり乾燥しすぎ
→ 打設前に地盤の状態を確認し、過乾燥なら高圧洗浄機で散水湿潤、過湿潤なら透水シートを設置(水抜きパイプを奥から入れる) -
打ち継ぎ部での不適切な処理(打ち継ぎクラック)
→ 打ち継ぎ面はエアー清掃で清掃し、高圧洗浄機でレイタンスを掃除したら素晴らしい! -
プラスチック製スペーサーの使用
→ 可能な限りモルタルと熱膨張係数の近いPCスペーサーなどのスチール系のスペーサーを使用する。 -
吹付厚の不均等性
→ 吹付け前にラス金網を適正に張り、所定厚さを確保。厚さ確認用のピンを設置し、出来る限り均一に仕上げる。(職人の技術による)

環境要因と対策
-
高温時施工(蒸発が早く収縮ひび割れ)
→ 打設後に散水養生やシート養生を行う。早朝・夕方に施工時間を調整する。(実際はかなり難しい判断とコスト上がる施工) -
低温時施工(凍害による微細クラック)
→ 気温5℃未満では施工を避ける。お湯割りにする。やむを得ない場合は防寒養生(シート・加温)。 -
乾燥風・直射日光下と影の混在
→ 打設後は湿潤シートで表面を保護し、急乾燥を防止する。(実際はかなり難しい判断とコスト上がる施工) -
周囲の湿度差による不均一乾燥
→ 局所的な日陰・風向きの影響を考慮し、全面を均一に養生。特に角部や端部は重点養生。(実際はかなり難しい判断とコスト上がる施工) -
外部からの振動や荷重による硬化不良
→ 初期硬化(打設後24時間程度)は荷重・振動を避ける。隣接工事や機械稼働の影響を調整する。
設計・構造要因と対策
-
打設厚さが不均一で応力集中(地盤の不陸が大きすぎる)
→ 事前に地盤を整形し、厚さを均一化。ラス金網や下地モルタル吹付(貧配合)で凹凸を調整してから本施工を行う。(コスト↑↑) -
異なる部材の熱膨張差による応力(プラスチック製スペーサーとラス金網)
→ 熱膨張係数の近い材料を組み合わせる。異種材を使う場合は、応力緩和のために目地や余裕寸法を設ける。

パッとで思いつく原因と対策です。
特に、砂などの材料の地域性はどうしようもありません。
そんな時は砂の量を減らすとか?上げるとか?地域によった配合比が意外と存在します。
その辺を見極めて行く事も大事かと思います。
あとは、水も結構な割合で悪さする事があるので気をつけて下さい。
それではまた。