皆さんこんにちは。
エンタです。
先日、発注者側の施工管理会社の社員?の方でしょうか。
注入の事でご指摘を受けました。

追って説明していきます。
1、削孔完了
2、インナーロッド抜管
3、アンカー挿入
4、注入ホースよりセメントミルク注入(ケーシング内置換注入)
5、オーバーフロー確認
6、アウターケーシングの抜管(定着部まで)
7、加圧注入 ココでご指摘

加圧圧力はグラウンドアンカー協会では0.2~0.4Mpaです。
しかし、今回この加圧の0.2Mpaが上がらなかった訳です。(実際は0.18Mpa程度です)
というのも、ケーシングの外から出てしまい圧がかからない状態です。
これはこれで仕方ないのでこれで終了しようとすると、年配の施工管理は???って感じです。
0.2上がっていないからケーシングの外からセメントミルクを上げるのが当たり前的な事をおっしゃるわけです。
私はそんなことは今までやっていないし、そういった文献や指針は無いですよ?。
と言い切ったところ、ご立腹・・・・w
終始高圧的な感じだったので私の言い方も悪かったのですが、なんだかねーw
久々にこんな高圧的な人見ましたw
確かにおっしゃることはわかります。
しかし、定着部にしっかり注入してしまえば自由長部は充填注入です。
ちょっと北海道なので資料が無いのであいまいですが、加圧はそれ程追う必要はない的な資料がどこかに。
そして、粘土層と岩盤については加圧の効果は薄いと言う論文もあります。(関係ないけど)
セメントミルクも1本分丸っと作っているのですが、場所によってはロスによって8割~9割程度場合があります。
なので、そんなにセメントミルクも作ってないです。って言ったら、そんなことは関係ないと。
また作ればイイ的な事をおっしゃるわけですw
おお、高圧先生だ!現場施工の事を一切考えない発言!
グラウトミキサーってそんな中途半端に作れないので、多く作って捨てるとゴミも出るんですよ?
お金もかかるんですよ?時間もかかりますね?それって効率良いですか?
って思ってますが言いませんけど、いくら施工管理でもひどいですよね~w
発注者は落札者と対等なんですよね?(あ、うち下請けですがww)
恐らく施工管理はお金とか効率とかは関係ないんですよね。ただ、施工が出来ているかだけですから。
だから、高圧先生が多くなるんでしょうか?いい人はもの凄く良い人なのに差が激しいw
加圧は上がらなくても、その後数本ケーシングを抜いて追い注入しています。
その際に外から出た水もセメントミルクに変わっています。
しかし、その時はもう帰って見ていない施工管理(17時を回っていたので)w
いやぁーなんだか愚痴を書いてしまいました。
またその施工管理来たら話してみますw良い現場にしようとしている思いは同じはず?
そのうち仲良くなれるかな??w
それではまた。




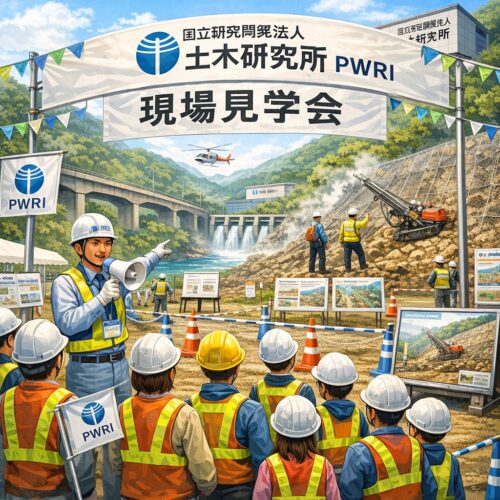




初コメントいたします。いつも楽しみに拝見させていただいております。
私も、某県において施工管理として働いているものです。
アンカー工施工経験がないので感覚論でしかないのですが、私なら、結局は最終的な緊張管理がOKならいいものであって、無理に圧力を確認する必要はないと考えます。
あくまで圧力は途中の「過程」の話ですので、結局は役所的には「過程」ではなく「結果(緊張管理)」でしかないですと思いますが・・・
いつもありがとうございます。
そうなんですけどね~。
しかし、勉強不足の方は特に細かく責任を取りたがらない方が多いのですべて仕様書通りを実践していきますw
まぁそれはそれで施工管理の仕事ですから否定はしません。
皆さんそれぞれの立場がありますから。
現場は大変ですけどね~~~~w
出来る事なら施工管理の職員同士で施工管理認識の統一をして頂ければ助かりますよね。
Aさんはこんなに言ったのに、Bさんは反対の事言ったって事はざらにあります。
いったいどっちなんだ!?ってw
まぁ管理値や規格値、仕様書を重視で行けばそれ程問題にはなりにくいですが、施工管理も人間ですので我も出ます。
ご立腹になったりするんですよwwwはっきり言って面倒wです。
今後ともよろしくお願いいたします。
役人の性格を見極めて管理を進める。大変ですよね。グラウトのケーシングからの外わまりで加圧かからず、気持ち分かります。今までなんとか言葉で逃げてきました。それより、エンタさんに質問^ – ^緊張管理でダイヤルゲージをデジタルにすると、役所の方も目につきやすく、読みやすく、報告書作成に苦労しませんか?立会い中に伸びの計測をメモにされたり、サインされたりと。不正な施工や管理はしてないですけど。荷重が持てばOKと言う私たちの考えと役人がメモした伸び量と報告書のデータが違うとか問題がありませんか。デジタルの方がカッコがいいですけど、アナログゲージの方が書類がだしやすいと思って僕はそうしてますけど、いかがでしょうか?
いつもありがとうございます。
ケーシングの外から出ても、こんなもんです。でOKでしょう!w
自信もっていきましょうw
デジタルでもOKだと思います。
というのも、仮にメモられて帰ったとします。
データ見たら上限値下限値に入らなかったとします。
その場合、やり直せば良いので、やり直しましたって報告すればOKです。
そのデータは範囲に入らなかったので無しでお願いします。って施工管理に言っていましたw
実際抜けていないのであれば、堂々としましょう!
PC鋼線が伸びない場合もあります。例えば自由長部の一部にミルクが入ったとかもありますから。
抜けていなければ訳の分からない言い訳もいくらでも出来るんです!w最終的に抜けてないからって言えます。
根本的に外でダイヤルゲージ付けて測定するような試験がおかしいだろ!って言ってもOKw
役所に、「ほら、風が吹いてもゲージ揺れるでしょ?試験の正確性なんて微妙ですよ?」でもOK
範囲に入らなかった場合は、施工管理の目の前で、最大値まで引張、初期荷重まで戻してください。
その差を確認して、入っていればOKですし、入らない場合は、測定器具の設置がほぼ悪いです。
ちなみに、私は施工計画書の段階ですべてデジタルノギス(1/100の精度)でストロークを測るとしているのでダイヤルゲージ付けません。
まぁ元請がどうしてもと言えば付けますが、付けても使用するデータはデジタルノギスですw
役所にも説明するのですが、ダイヤルゲージをPC鋼線に対し正確に水平と鉛直に設置することが物理的に出来ない。
なので、デジタルノギスを使用しています。その方がデータも良いです。と説明しています。
あとは技術者の報告書作成能力に頼るだけですね!!w
今後ともよろしくお願いいたします。