皆さんこんにちは。
エンタです。
先日衝撃を受けた話です!
めっちゃ衝撃でしたw
以前に似たような記事を書いたんですが、覚えていますか?
コレです。

うちに動力(200V)の電源を入れるべく電気工事士(プロ中のプロで有資格者)の方と話していました。
私「アースは長いアース棒を用意すればイイですか?」
電気工事士「まぁ、あそこに置いてある鉄筋で良いですよ」
私「え?ええええええ!」
電気工事士「ん??」
私「鉄筋で良いんですか!!????」
電気工事士「はい、問題ないですよ。通電さえすれば」
私「それは工事的に問題ないんですか??アース棒じゃなくてもOKなんですか??」
電気工事士「大丈夫です。アース棒って実は丸棒鉄筋に銅メッキしてあるだけなので同じなんです。」
「丸棒鉄筋に銅メッキしてあるだけ!!」
私「じゃぁ普通の鉄筋でも問題ないって事ですか!?」
電気工事士「はい。問題ないのですが、錆びてはだめです。なので銅メッキだと青錆びなので朽ちないのでOKになります。
なので、あそこにある亜鉛メッキでも抵抗値さえクリアできれば何ら問題ありません。」
私「じゃぁ今まで鉄筋にアース線巻いて打ち込んでた時にゼネコンの安全に怒られたのは何だったんでしょうか?w」
電気工事士「おそらく知識不足と、アース棒と言う製品名のアース棒を使いなさいと言う指示だと思いますよw」
電気工事士「我々も仮設の時は鉄筋も使用しますし、本設でも使用する事いっぱいあります。」
電気工事士「しかも中が鉄じゃないと打ち込めないですよ!銅ばかりのアース棒だとすぐに折れますよw」
私「ですよねぇ~~~~!w」
って事らしいです。
まぁ出来れば鉄筋に上部に穴を開けてアース線がしっかり入っている方が望ましいそうです。
もっとできればアース線を溶接かロウ付けかハンダ付けが最強らしい。(ここが大事な所だと思います。)
仮に鉄筋にそんな加工をしてあった場合でも、労働基準監督所が来ても絶対に大丈夫だそうです。
電気工事で敷いて使うアースなどもあるらしく、結局は表面積で抵抗値を稼げれば問題ないと言う事でした。
結局は通常の細いアース棒を使用するよりも、
太くて表面積のある異形鉄筋を使った方がアースをしっかり取っている事になるそうです。
目から鱗と言うか、知識不足でしたね~w
まぁ我々電気屋では無いのでアレですが、大手ゼネコンの安全管理が全て合っているとは限らないと言う事ですね。
今回非常に勉強になりました。
ただ、異形鉄筋だと抜くのに大変なのでやっぱり丸鋼が良いですよねw
丸鋼を亜鉛メッキして使えるので今後はそう言う方向で行こうと思います。
無駄にお高いあのアース棒を使用する必要はないと言う事ですね!(それ程高くは無いですけどw)
今度イイ感じの作って皆さんに披露しますね!
それではまた。




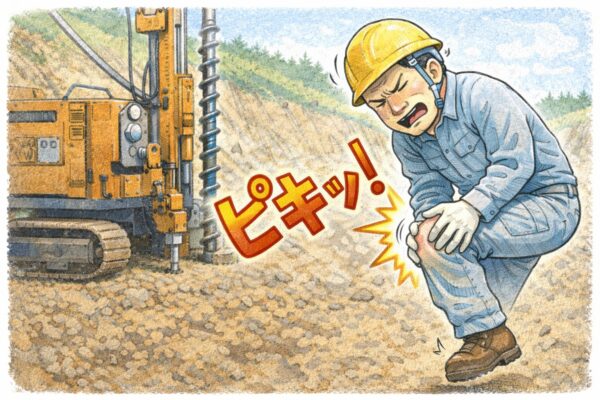



工事士の方がおっしゃる通り錆びない材料で抵抗値をクリアしてしまえさえすればいいのです。
ただし、この錆びないというのが曲者で、各々の判断に委ねた結果錆びてしまいましたーとなると非常に面倒なことになります。
変なところにアースを接続されたがために配管が電蝕を起こしてしまった、異常に早い劣化で数年後にはアースとしての機能を失ってしまっていた、などもあり得るわけです。
そのため、標準化の一環として「専用のアース棒を使用せよ」という形で統一させるわけです。
(一定以上の性能を確保するために施工方法もうるさく口を挟まれるのではないかと思います。)
事故を防ぐためには個人の技量を信用しないことが一番ですから。
仰る通りですね。
個人の技量よりも統一の製品が堅いですし、言い訳もw
しかし、アースの概念がこの時に吹っ飛びましたね。
やはり餅は餅屋。
非常に勉強になったアースの話しです。