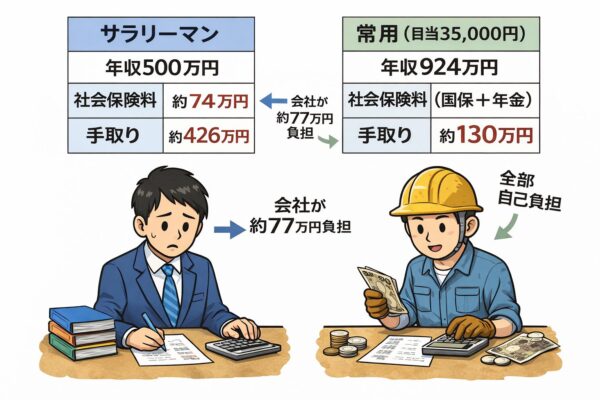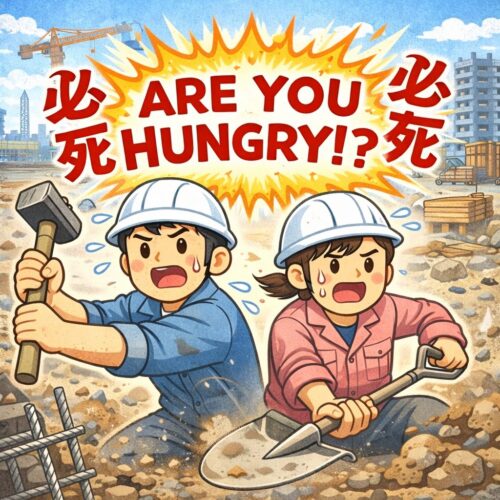皆さんこんにちは。
エンタです。
法面屋は知っていて欲しい、現場でよく使う粘着力cと内部摩擦角φの話し(その1)
法面屋は知っていて欲しい、現場でよく使う粘着力cと内部摩擦角φの話し(その1)
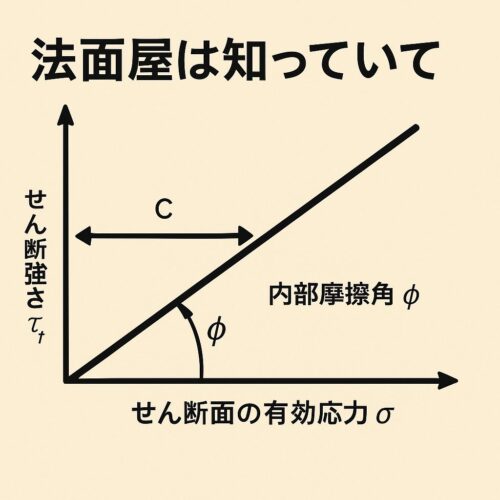
前回は土の強さの事を書きました。
で、今回は粘着力c(kN/m2)を掘り下げていきます。
粘着力の定義
粘着力(cohesion, 記号:c)とは、土粒子どうしが相互にくっつこうとする力を数値化したものです。
単位は kN/m² で表され、地盤の強度特性を評価する際に欠かせない指標です。
この「くっつき力」が大きければ、法面や掘削面は崩壊しにくく、逆に小さい場合は土砂が自立できずに崩れやすくなります。
粘着力のイメージ
砂質土(乾燥砂) → 粘着力 ≒ 0、サラサラで崩れやすい。
粘性土(粘土質) → 粘着力が大きい、壁面が自立しやすい。
例えば、砂場で「砂だんご」を作るとき、乾いた砂では形が保てませんが、水分を含んだ砂や粘土なら固まります。
この「固まる性質」が 粘着力 ってことですね。

数値の意味
例えば、c = 20 kN/m² の場合、
1㎡のせん断面に対して、20 kN(約2トン)の力で土が崩れないように保持していることを意味します。
具体的なイメージは1 m² のせん断面を考えると、
20 kN ≒ 2,000 kgf(約2トン)の荷重 に対して、崩壊せずに耐えられる“付加的な強さ”を持っている。
この強さは「有効応力(σ’)」や「摩擦角(φ)」がゼロであっても存在する“粘着成分”として現れます。
せん断強さ式:=+σ′⋅tan
ここで σ’ = 0 のときでも、τ = c となり、20 kN/m² の抵抗力が発現する。
設計上はモール・クーロン破壊基準に基づき、
せん断強さ τ = c + σ’・tanφ(ここで σ’:有効応力、φ:内部摩擦角)として評価され、c はその中の「一定の粘着成分」として扱われます。
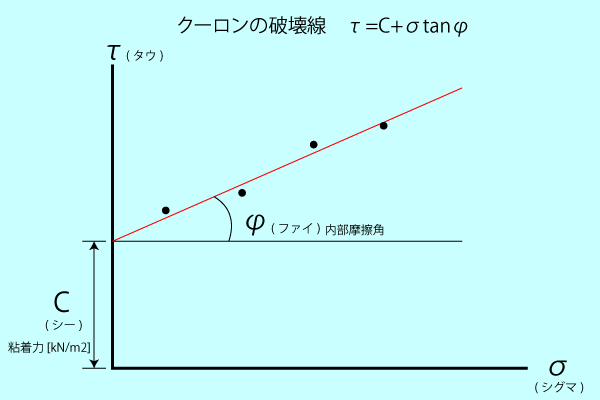
なぜこれが重要か?
法面安定計算:粘着力が大きければ安定度が高くなる。
掘削の可否:自立時間の推定に必要。
基礎地盤設計:支持力・すべり破壊の判定に必須。
特に、現場では 粘着力がゼロに近い砂質土 か、大きな粘着力を持つ粘性土 かを見極めることが、施工段階での重要ポイントになります。
粘着力 c[kN/m²]= 土が持つくっつき力。
砂質土ではほぼゼロ、粘土では大きい。
数式では「モール・クーロンの式」の定数。
法面での安定計算では必須項目。
そして技術者として押さえておきたいのは、c は土の種類や含水比によって大きく変化するという事。
だからこそ水を抜く!って事の重要性が分かりますよね。
それではまた。