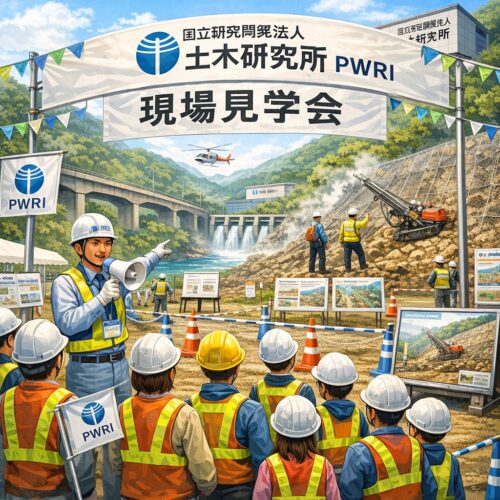皆さんこんにちは。
エンタです。
グラウンドアンカー工を簡単に説明してみようと思います。

~緊張力で地盤を固定する見えない力~
グラウンドアンカー工は、地盤や構造物を“引っ張る力”(緊張力)で固定・安定化させる工法です。
斜面の崩壊や擁壁の転倒・滑動を防ぐため、目に見えない地下に“アンカー”を埋め込んで構造物を支える、極めて重要な地盤補強技術です。
🔧 グラウンドアンカーの基本構造
グラウンドアンカーは、以下のような構造で成り立っています:
| 部位 | 説明 |
|---|---|
| 定着部(定着長) | アンカーの先端が地盤と強固に接着される部分。ここで緊張力を周面摩擦によって受け止める。セメント系グラウトで地盤と一体化させる。 |
| 自由長 | 定着部と地表部をつなぐ部分で、緊張力を伝える役割。通常はPVC管などで覆って変形しないようにする。 |
| 頭部(アンカーヘッド) | 地表部に設置され、構造物や受圧板と接続される部分。ここで緊張力をクサビやナットによって定着(固定)する。 |
| 受圧板 | 擁壁や構造物とアンカーを接続する鋼板。アンカー力を面として構造物に伝える。 |
⚙️ 原理:緊張力によって地盤や構造物を“抑える”(抑止工)
グラウンドアンカーの原理はとてもシンプルで、
「地盤の深部に定着させたアンカー体を引っ張り、その力で構造物を押さえつける」(挟む)というものです。
▸ 簡単な構造
-
アンカーを斜めにボーリング(削孔)して挿入
-
アンカー全体にグラウト(セメント系)を注入し、地盤と一体化させて「定着部」を形成(自由長部はホース内で自由に動く)
-
アンカーヘッドから油圧ジャッキ等で緊張力(テンション)を与える
-
緊張力がアンカー定着部から地盤に伝わり、擁壁や斜面を抑える力が働く

このようにして、地山のすべりを防止したり、擁壁の浮き上がりや倒れを抑えることができます。
🧱 なぜ「緊張力」で支えるのか?
地盤の補強と言えば“押さえつける(圧縮)”イメージがありますが、グラウンドアンカーは真逆の「引っ張って支える」発想です。
その理由は:
-
地中深くの強固な地盤に定着させれば、大きな抵抗力が得られる(周面摩擦抵抗)
-
アンカーはコンパクトで、地表のスペースを取らない(工事はまぁまぁ大きくやってるけどw)
-
擁壁や法面が後から追加補強できる
というメリット

🌍 グラウンドアンカーが活躍する場面
-
急傾斜地の法面安定
-
擁壁の滑動・転倒防止
-
地すべり対策工事
-
トンネル・ダム・高架橋など大規模インフラ
- 土留めでの仮設工
鉄筋挿入工よりはちょっと面倒な工事ですが、安定性はバツグンですね。
ココに水抜きボーリング工を設置するともっと安定しますし、突発的な大雨にも対応出来ます。
それではまた。